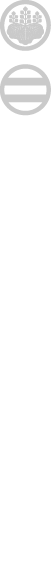関連資料
林光院の鶯宿梅
臨済宗大本山相国寺の塔頭である林光院の庭園には、平安朝文化の優雅な時代思想を反映する代表的なエピソードの主人公である「鶯宿梅」という名梅が現存する。
「大鏡」によれば、村上天皇の天暦年間(947―956)、御所の清涼殿の梅の木が枯死したので、それに代わる梅の木を探し求めさせたところ、西の京の紀貫之の娘の屋敷の梅がその選に応える名梅であるというので、天皇の勅令に依り御所に移植されることになったのであるが、別れを惜しんだ娘は短冊に
勅なればいともかしこき鶯の
宿はととはばいかがこたへむ
という一首を詠み、梅の枝に懸けておいたところ、この歌が天皇の目にとまり、その詩情を憐れんで元の庭に植え返されたという。(大鏡・拾遺和歌集)
その時からこの梅が「鶯宿梅」、又は「軒の紅梅」と称せられて、「みやび」や「もののあはれ」と云うことを尊んだ王朝の優雅な時代精神を現す代表的物語として、後生にまで喧伝されるに至ったのである。
応永二十五年(1418年)正月、足利三代将軍義満(相国寺開基)は、二十五歳で早世した第二子の義嗣(林光院殿亜相孝山大居士)の菩提を弔うために、夢窓国師を勧請開山として、京都二条西の京の紀貫之邸の址地に林光院を開創した。

以後、林光院境内樹木として、この「鶯宿梅」は寺と消長を共にすることになったのである。
林光院のその後の二度にわたる移転の度毎に「鶯宿梅」も又移植されねばならぬ運命を担い、霜雪一千有余年、その幹は幾回か枯死したが、歴代の住職の努力によって、接ぎ木から接ぎ木へと、現代に至るまで名木の面目を維持して来たのである。
花は三十六枚もの花弁を有し、一名、「軒の紅梅」と称せられる如く、つぼみの間は真紅で開花と共に淡紅に変じ、最後に純白に移っていく所謂、仙品である。
更に、この「鶯宿梅」にまつわる歴史上の人物とのエピソードも数多く伝えられている。文禄征韓の役に活躍し、のち林光院の外護者となった島津家久はこの梅を深く愛し、参勤交代の途中林光院に立ち寄り、
うぐいすの春待宿の梅がえを
おくるこころは花にぞ有哉
と詠んだ。また徳川中期、林光院を兼務した大典禅師と親交のあった煎茶の師匠、あるいはむしろ歴史的奇人として有名な売茶翁も、一時この寺に寄寓してこの梅の実を梅干にして愛蔵し、雅客文人に贈ったと伝えられる。明治の初年、富岡鉄斎も扇面に「鶯宿梅」を描き、花だけ本物をつんで糸でぬいつけた軸物が、いまも林光院に宝物として保存されている。